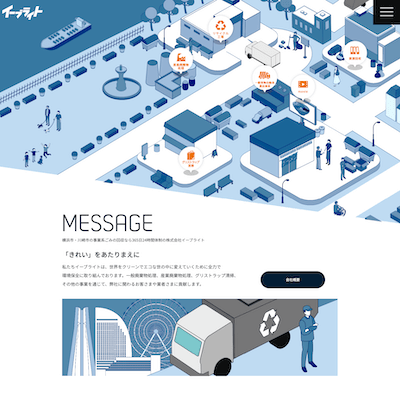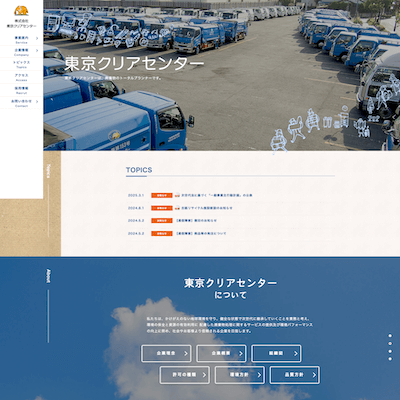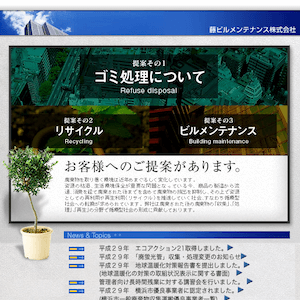近年、産業廃棄物の適正管理において「電子マニフェスト」の導入が注目を集めています。これまで主流だった紙マニフェストと比べ、より効率的かつ透明性の高い管理が可能となるため、導入を検討する企業も増えてきました。そこで、今回は電子マニフェストの仕組みやメリット、そして普及の現状について詳しく解説します。
電子マニフェストとは
電子マニフェストとは、産業廃棄物の処理に関する情報をインターネットを介してやり取り・管理する仕組みです。排出事業者が産業廃棄物を委託する際、処理業者との間で「いつ・どこで・どんな廃棄物が・誰によって・どう処理されたのか」を記録し、報告・管理するためにマニフェストが必要とされます。従来はこの手続きがすべて紙で行われており、記入ミスや紛失、回収の手間といった課題がありました。このような課題を解決するために導入されたのが、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが運営する電子マニフェストシステムです。
電子マニフェストでは、紙のやり取りを省略し、パソコンやネットワークを活用して処理情報を即時に記録・確認できます。排出事業者は、廃棄物が適正に処理されたかをリアルタイムで把握できるほか、行政への報告もスムーズにおこなうことが可能です。
また、電子マニフェストの利用にはJWNETへの加入が必要です。インターネットの操作に慣れる時間が必要ですが、慣れてしまえば手作業よりもはるかに効率的といえます。
電子マニフェストのメリット
電子マニフェストの最大の魅力は、業務の効率化と法令遵守の確実性にあります。まず紙マニフェストでは、伝票を作成し、排出・収集・処分それぞれの事業者で保管・確認・返送する必要がありました。そのため、記入ミスが起こったり、返送が遅れたりすることで、最終処分の確認が遅れたり、行政指導を受けるリスクが生じたりしていたのです。一方で電子マニフェストでは、入力情報がリアルタイムで共有されるため、記入ミスや伝票の紛失といった人為的なミスが減少します。
さらに、各工程の完了報告もシステム上で簡潔におこなえるため、全体の進捗を瞬時に把握することが可能です。とくに、多くの拠点や複数の委託先を抱える企業では、紙のように一件一件確認する必要がなくなり、大幅な業務削減につながります。
また、行政報告に関しても従来は年に一度、紙で集計して報告書を作成・提出する必要がありました。しかし、電子マニフェストを利用していれば報告が不要なので、報告作業の省力化が可能です。
そして、電子マニフェストは、情報処理センターにて5年間保存されるため、事務作業も大幅に軽減されます。法改正への対応も早く、最新版の制度に準じた形式で記録・管理できるため、監査対応やリスクマネジメントの観点からも信頼性が高まることでしょう。
さらに、電子マニフェストでは排出から最終処分までの全行程が可視化されるため、排出事業者としての責任を果たしやすくなります。
不適正処理が行われていないかをシステム上で即座にチェックできるため、コンプライアンスの強化にもつながるのです。環境配慮の姿勢が求められる現代においては、企業としての社会的責任を果たす手段のひとつとしても注目されています。
電子マニフェストの普及率
電子マニフェストの導入は年々進んでいますが、すべての事業者が移行しているわけではありません。公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の発表によると、2023年5月時点での電子マニフェストの利用率は全体の約78%にとどまっており、残りの約22%は依然として紙マニフェストを利用している状況です。この数字からもわかる通り、電子化の波は確実に進んでいるものの、業種や企業規模によって導入のばらつきがあります。とくに、収集運搬、処分会社では比較的電子化が進んでいる傾向にあります。
一方で、小規模事業者や廃棄物の発生頻度が少ない事業所では「手続きが煩雑そう」「システムの操作が難しそう」といった理由で、導入を見送っているケースもあるようです。しかし、近年では行政による電子化の後押しも強まっており、特定の排出事業者に対して電子マニフェストの導入が義務化されています。
JWセンターでは、電子マニフェストの利用促進に向けた各種セミナーや、導入支援のためのマニュアルの提供などもおこなっており、導入に不安のある事業者でも比較的スムーズに切り替えが可能です。
紙でのやり取りに比べ、時間やコスト、人的ミスの削減といった多くのメリットを享受できることから、今後は電子マニフェストがスタンダードになる日も遠くはないでしょう。